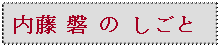

『柿本人麻呂論―複式長歌の誦詠考―』(内藤 磐・明治書院・1984,9 国文学研究叢書)
ある日、柿本人麻呂のウタを、四つ折りにした紙に、なんとなく書きつけていた。その時、異伝の部分を本文の
横に書くと、「唱和・誦詠」の形式に見えてきた。声明やグレゴリオ聖歌やギリシャ悲劇の「コロス」等を連想
させた。これが原点である。
この柿本人麻呂のウタの特徴は、“歌われた古代のウタ”の姿そのものではないのか、と考え、それは次々と私
の中で展開していった。古代にも、ウタは節をつけて歌う場があった・・・のではないのか。これは古今東西多く
の例がある。今までの「異伝誦説」や「推敲説」に対する新見解を書き下ろしたのが、この著書である。

『上代歌謡演劇論』(内藤 磐・明治書院・1987,10 角川源義賞国文学部門年度候補)
「古事記」と「日本書紀」を“文学”と“歴史”というような先入観にとらわれず、二つの書物の伝承を虚心に
みたときに、何がみえはじめるか…天武朝の初めに集められた「能く歌ふ男女・侏儒・伎人(きにん)」の存在をも
考え合わせると、歌われていた古代のウタの現場が、私には生きいきと息づいて見えてくるのである。
侏儒・伎人の役割を考えると、「歌舞演劇」の演じられた「ウタの場」が、あったのであろうことは想像にかたく
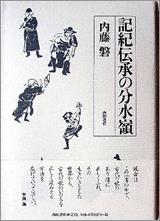 ない。この『上代歌謡演劇論』は、『柿本人麻呂論―複式長歌の誦詠考―』を原点として、より発展させて自由
ない。この『上代歌謡演劇論』は、『柿本人麻呂論―複式長歌の誦詠考―』を原点として、より発展させて自由
に私の「ウタの場」を論じたものである。出版当初は「余りにも斬新で、批評できない。」との“批評”も頂いた
ことは、今でも懐かしく思い出されるが大方は故人となられた。近年に至り、国文学が若者には不人気となって
いるにも関わらず、必読図書にあげて頂いているのは光栄であると思う。本年(2018,1)出版した『難波津のウタ』
は、この『上代歌謡演劇論』を実証したものである。
『記紀伝承の分水嶺』(内藤磐・西田書店・2002,10 早稲田大学学術図書出版助成)
 「古事記」と「日本書紀」は、ほとんど同時代に編纂されている。その中には、多くの“疑問”が残されている
「古事記」と「日本書紀」は、ほとんど同時代に編纂されている。その中には、多くの“疑問”が残されている
と私は考えてきた。両書は、個々の存在ではなく、密接な関係にあると思う。特に両書にも、多くのウタが含ま
れており、その半数以上が「重出」しているのは見逃せない。これは記と紀との成立の“鍵”を秘めているとい
えるであろう。万葉古代学研究所共同研究員の時に、書き下ろしに今まで論じてきたものを少し補い著書にした。
「序」は万葉文化館館長・文化勲章受章者の中西進先生が「私が書くよ。」と言われて書いて下さった。肩書は無い。
また、表紙は私の所蔵している「正倉院ご宝物の模写写真」を、妻がアレンジしてデザインした。東大寺管長が、
電話で写真使用を快諾してくださった。皆さんのお蔭で出版できたことに、深く感謝している。

『古事記論集』(古事記学会編・おうふう・平成15年5月・12,000円+税・分担執筆)
目次
第一部 古事記の神々
第二部 古事記の氏族伝承
第三部 古事記の世界
太安万侶の道教認識についての一考察―序文の「混元既凝」を中心に― 薬 会
天の御柱の解釈について 勝俣 隆
黄泉国と妣の国と根の堅州国 山田 永
古事記日向三代巻考―日向三代巻の意義(1)― 高橋 一夫
記紀歌謡の織りなす世界―カタリにおけるウタの役割―
内藤 磐
『古事記』反乱物語の「知」と易学 中尾 瑞樹
「根国」の展開―日本書紀神代上第五段[本伝]と各一書、及び古事記との相関― 榎本 福寿
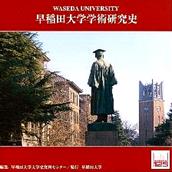 『古事記』系図記述論序説―日子坐王「娶生」系譜の一段面― 板垣 徹
『古事記』系図記述論序説―日子坐王「娶生」系譜の一段面― 板垣 徹
『高蒔絵三十六歌仙額』(静学堂・1999,9
早稲田大学特定課題研究・代表 内藤 磐)
(共著者・内藤典子・内藤美奈・内藤 亮)
「高蒔絵三十六歌仙額の和歌―「十八番歌合せ」としての構想―
「高蒔絵三十六歌仙額」奉納の時代背景―「柳川一件」の再評価―・・・内藤 磐・内藤 亮(他・共著者略)
対馬に残る全36面揃いの古満蒔絵「三十六歌仙額」である。全国唯一の“高蒔絵”で、正保2年(1645)
三代将軍・徳川家光時代に、二代対馬藩主・宗義成により、現・八幡宮神社に奉納された。私たち家族4名
は、それぞれの専門分野から、「高蒔絵三十六歌仙額」の複合的調査研究を5年間に10回渡島して行った。
私の調査研究費の一部は、早稲田大学から支給された。行政・神社共に「覚書・委任状」などを取り交わした。
しかし止むをえない事情から、調査研究結果を無為にしないために、家族一同で「静学堂」を設立し出版した
本である。
何よりも共著者一同が危惧していたのは、朝鮮通信使・対馬藩史・徳川幕府政治史とも深く関るこの額が、
今もって何の保護処置もとられていないことであった。国外流出や散逸は何としてでも食い止めなければ、日
本の漆工芸の損失は大きいと思っている。この調査報告書が公に認められ、御購読者各位のご支援により対馬
市の「文化財指定」を受けたことは業績ではあるが、更により重要な保護を要請したいと行動している。
「早稲田大学学術研究史」(CD・早稲田大学刊)
早稲田大学創立以来の主な学術研究をコンパクトにまとめたCDである。
身近に接してきた文学部創始者の一人「窪田空穂」について、評伝を書いた。 窪田空穂は、
教科書にもでてくる有名な歌人である。
私は大学院時代に『窪田空穂全集』の編纂を手伝わせて頂き、カメラとライトをかついで方々
に出かけたのも、懐かしく思い出している。ご子息・窪田章一郎先生は、私の指導教授であり、
ご著書『西行の研究』(学位論文)は、僭越ではあるが「名著」である。
早稲田大学の深く広い学術研究の歴史を、皆様に知って頂きたくお勧めしたい。
トップ 共著へ 万葉古代学研究所のこと 研究業績 記紀伝承の分水嶺 静学堂の表紙へ